東日本大震災から2年以上が経過して・・・。
被災者が気にしてるのは、「3.11の風化」です。
![イメージ 1]()
マス・メディアの2周年報道キャンペーンも、終わりました。
でも、僕の発信してる【被災地の漁師の報告】については、震災後、2年の現地の報道なり画像を見て、逆に「あんななに、復興が遅れていたなって・・。初めて知りショックを受けました。改めて、これからの支援の必要だと感じました」という、反応が多く寄せられたのです。
それまで、私は震災直後から2年経過して、当ブログやTwitter、Facebookでも、「風化は進んでる」と強く感じていました。
でも、密かに、なんとなくですが、「この現実が報道されれば、またきっと・・。」という感じはしていたのです。
2年目経過しての報道は、「ノッペラとした津波襲来地域の被災地映像が報道されました」このことによって、驚いた国民はやはり多かったのです。
マス・メディアの2周年報道キャンペーンも、終わりました。
でも、僕の発信してる【被災地の漁師の報告】については、震災後、2年の現地の報道なり画像を見て、逆に「あんななに、復興が遅れていたなって・・。初めて知りショックを受けました。改めて、これからの支援の必要だと感じました」という、反応が多く寄せられたのです。
それまで、私は震災直後から2年経過して、当ブログやTwitter、Facebookでも、「風化は進んでる」と強く感じていました。
でも、密かに、なんとなくですが、「この現実が報道されれば、またきっと・・。」という感じはしていたのです。
2年目経過しての報道は、「ノッペラとした津波襲来地域の被災地映像が報道されました」このことによって、驚いた国民はやはり多かったのです。
「日本人の被災地を支援したい気持ちにどのような変化」ーがあるのでしょうか・?
公益社団法人の「助けあいジャパン」の調査によると・・。
------------------------------------
助けあいジャパン「東日本大震災後の助けあい実態調査」
概要調査手法:インターネット調査
調査地域:岩手県、宮城県、福島県を除く日本全国44都道府県
調査対象:15歳~69歳の男女個人1,000名(国勢調査の人口構成比に基づき割り付け)
調査日程:2013年2月15日~20日
調査機関:株式会社サーベイリサーチセンター(東京都荒川区西日暮里2-4-10)※この調査に関するお問い合わせは、こちらのフォームよりお願いします
http://tasukeaijapan.jp/?p=32483
被災地(岩手、宮城、福島)以外に住む15~69歳の男女に聞いたところ、震災直後に被災した人や地域を支援したい気持ち(強く+やや)を持っていた人は83.6%に対し、現在も持っている人(強く+やや)は76.6%。「強く持っている」人の割合は下がっているが、支援したい意志は大きく低下していないことが、公益社団法人「助けあいジャパン」の調査で分かった。
調査対象:15歳~69歳の男女個人1,000名(国勢調査の人口構成比に基づき割り付け)
調査日程:2013年2月15日~20日
調査機関:株式会社サーベイリサーチセンター(東京都荒川区西日暮里2-4-10)※この調査に関するお問い合わせは、こちらのフォームよりお願いします
http://tasukeaijapan.jp/?p=32483
被災地(岩手、宮城、福島)以外に住む15~69歳の男女に聞いたところ、震災直後に被災した人や地域を支援したい気持ち(強く+やや)を持っていた人は83.6%に対し、現在も持っている人(強く+やや)は76.6%。「強く持っている」人の割合は下がっているが、支援したい意志は大きく低下していないことが、公益社団法人「助けあいジャパン」の調査で分かった。
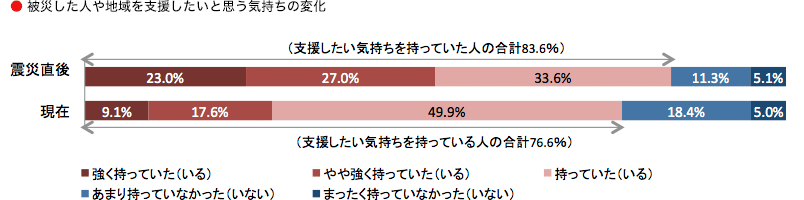
この、調査を見るとすこし、「ホッと」しますね。
被災地を支援したい人の割合を年代別にみると、若年層がやや低い。居住地別では、被災地から距離がある四国や九州で高い。この結果について、助けあいジャパンは「世代や被災地からの距離を問わず、広く支援の気持ちが広がっていることがうかがえた」としている。
被災地を支援したい人の割合を年代別にみると、若年層がやや低い。居住地別では、被災地から距離がある四国や九州で高い。この結果について、助けあいジャパンは「世代や被災地からの距離を問わず、広く支援の気持ちが広がっていることがうかがえた」としている。
●今後の支援活動としては・・。
実際に、被災地を支援した人はどのくらいいるのだろうか。震災から半年の間に「支援した」人は68.5%に対し、半年から1年後では40.0%、1年後から2年後までは31.0%。つまり、支援する意志は低下していないものの、実際に行動した人は大幅に減少している。
でも、これは仕方がないことです。支援者自身の職場や生活などなどありますから・・。
でも、これは仕方がないことです。支援者自身の職場や生活などなどありますから・・。
被災地を支援したい人にどのようなことをしたのかを聞いたところ。
震災直後は「金銭的な支援」が多かったが、現在では「被災地の物品購入」や「観光支援」などに移行していることが分かった。
今後、支援活動をしたいと考えている人はどのくらいいるのだろうか。全体の75.9%は、何らかの支援活動をしたいと回答。
具体的には「被災地の物産・食品を意識的に購入する」(38.4%)と「義援金の寄付や募金など、金銭的な支援を行う」(34.5%)が目立った。年代的にみると、50~60代は被災地の物品購入や観光支援の意志が高く、40代はイベント参加、10~20代はボランティアへの参加意向がうかがえた。
この公益社団法人の「助けあいジャパン」のコンセプトは
『助けたい気持ちがある人の、ヒントやきっかけになること。
そして、過去にしないこと。いっしょに未来を作ること。』
まさに、被災者ニーズとピッタリですね。
-------------------------------------------
この、調査結果を見て、ホントに日本人はありがたいなあ・・。
つくづくそう思います。
言葉で簡単に、「ありがとうございます」では足りない
つくづくそう思います。
言葉で簡単に、「ありがとうございます」では足りない
「ありがとう」なんです。
私は普段も
当ブログ、Facebookなどでは、転載拡散、リツート、FBシェアなどはもとより、色々な支援を頂いています。
インターネットの中でも、初めは拡散やシェアだったものが、リアルに行動に移ってきてるのを感じます。
それは、「実際に被災地を見たいので」という行動が多く見られます。
私のところにもの、頻繁に誰かが訪れてくださいます。
私は普段も
当ブログ、Facebookなどでは、転載拡散、リツート、FBシェアなどはもとより、色々な支援を頂いています。
インターネットの中でも、初めは拡散やシェアだったものが、リアルに行動に移ってきてるのを感じます。
それは、「実際に被災地を見たいので」という行動が多く見られます。
私のところにもの、頻繁に誰かが訪れてくださいます。
そこでさて、ふと思ったのですが・・。
昔、うちのムラで、「中、高校生の農林水産業の体験学習」ってのがありました。これの、「被災地体験学習版」みたいな企画があってもいいではないか・・・?と思ったのです。
昔、うちのムラで、「中、高校生の農林水産業の体験学習」ってのがありました。これの、「被災地体験学習版」みたいな企画があってもいいではないか・・・?と思ったのです。
今、「島国日本において今、専門家によって叫ばれている東南海トラフ、都市直下型の地震や津波」の関心はとても、高いものになっています。
つまり、「3.11から学ぶ、防災、自分の命は自分で守る」という点で言えば意義ある修学旅行になると僕は想います。
「3.11を教訓にするほか、震災対策や減災について被災者から学ぶ事」は、人を真剣にさせると思います。
生々しい、現地で、実際に津波で流され助かった人の生の声は非常に多いのではないでしょうか・・?
やはり、団体としての「修学旅行」はそれなりの、目的を持ってくるので、どちらにもメリットがあり、意義あることだっと思ったのです。
さて、そんな中・・・・・。
2013年3月30日付けの「石巻新聞」でみたのですが・・。
これは、3.11東日本大震災で最大の被災地石巻市が震災後、「防災教育を兼ねた修学旅行先(一部社会見学)としてにわかに注目を浴びている」というにです。
石巻観光協会のまとめによると、2012年度は小中高合わせて27校、1920人が訪れ、13年度も既に15校、865人の予約が入っているのです。
![イメージ 6]()
![イメージ 7]()
2013年3月30日付けの「石巻新聞」でみたのですが・・。
「石巻、修学旅行客が急増 最大被災地に学ぶ 新年度既に15校予約」ってのがありました。
http://ishinomaki.kahoku.co.jp/news/2013/03/20130329t13008.htm
http://ishinomaki.kahoku.co.jp/news/2013/03/20130329t13008.htm
これは、3.11東日本大震災で最大の被災地石巻市が震災後、「防災教育を兼ねた修学旅行先(一部社会見学)としてにわかに注目を浴びている」というにです。
石巻観光協会のまとめによると、2012年度は小中高合わせて27校、1920人が訪れ、13年度も既に15校、865人の予約が入っているのです。
急増する状況に驚きを隠しきれない観光関係者は・・・・。
「震災の教訓を学んでもらうほか、石巻の魅力を感じ取ってもらいまた来てほしい」と話し、歓迎ムードを盛り上げていきたいと語っていました。
「震災の教訓を学んでもらうほか、石巻の魅力を感じ取ってもらいまた来てほしい」と話し、歓迎ムードを盛り上げていきたいと語っていました。
3月31日までの2012年度に、度石巻を訪れたのは小学校15校、中学校1校、高校11校。都道府県別では山形県が14校と最も多かったようです。
遠方では福岡県の私立修猷館高校や福岡大付属大濠高、大阪電気通信大高などが来ています。
被災地の現状を見て、教訓にするほか、震災対策や減災について学ぶことが目的らしいのです。
被災地の現状を見て、教訓にするほか、震災対策や減災について学ぶことが目的らしいのです。
迎える地元では、石巻観光ボランティア協会(斎藤敏子会長、24人)の会員たちがバスに同乗し、震災時の様子や復興状況、津波の恐ろしさなど、体験を交えて話している。
新年度に予約を済ませた学校のうち、酒田市平田小、琢成小、鶴岡市京田小、栄小は2年続けての来訪しています。
平田小の桜井浩之教頭は「毎月11日を震災の日と決め、教訓を風化させない取り組みをしており修学旅行もその一環。現地を見ることは何より勉強になる」と被災地を訪れる意義を強調していたと伝えています。
斎藤会長は「震災により来客が増えるという皮肉な結果だが、訪れていただくのは喜ばしいことです。
『また石巻に来たい』 と言われるような対応をしたい」と話しています。
後藤宗徳石巻観光協会長は「若いうちに自分の目で見て、どうやって命が守られ、守られなかったのかや、悲しみから立ち上がる努力などを学び将来に生かしてほしい」と話し、積極的に修学旅行を受け入れたい考えです。
石巻地方の観光施設や宿泊施設は壊滅的な被害を受けた中、復旧に向けた取り組みが少しづつ進んでおり、将来的には宿泊や食事、買い物をしてもらえるような環境整備を、行政も力点をおくのではないでしょうか・・?
僕のところに訪れたくださった方は、必ず言う言葉があります。
それは、「被災地を画像、映像で見ていたのと、全然違うと・・・・。」
それでも、今はもう瓦礫は片づけられて震災、津波の生々しさは、なくなっています。
そして、必ず言うことは「国家は何をしてるのだ!!」という怒りの声です。
僕は、そんな方々にいつもこう言います。
「被災地の現地で感じてください。聴いて、自分で想像して、そして想ってください。」
そして「多くの人に伝えて欲しいのです。」
「正しく、伝える事こそ復興の大きな支援になりますから」と・・・・。
それは、「被災地を画像、映像で見ていたのと、全然違うと・・・・。」
それでも、今はもう瓦礫は片づけられて震災、津波の生々しさは、なくなっています。
そして、必ず言うことは「国家は何をしてるのだ!!」という怒りの声です。
僕は、そんな方々にいつもこう言います。
「被災地の現地で感じてください。聴いて、自分で想像して、そして想ってください。」
そして「多くの人に伝えて欲しいのです。」
「正しく、伝える事こそ復興の大きな支援になりますから」と・・・・。